 |
 |
 |
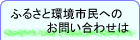
 |
場所 神奈川県綾瀬市
連絡先 09080044166
Mail お問い合わせ
パンフレットはこちら ⇒  |
|
 |
|
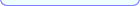 |
 |
 |
 |

AcrobatReader は、こちらから入手して下さい。
|
|
 |
 |
目久尻川の名前について(あやせ昔話より) |
 |
小園橋そばの河童の像を例にとり、昔この川に住んでいた河童が農作物を荒らしたのに住民は困りはてて、ある日河童をとらえその目をくじり取ったという昔話をし、それから目をくじるが転じて目久尻川といわれてきたことを話しています。 |
 |
暴れ川といわれた事について |
 |
昔、この川は今の様に水の流れがスムーズでなく、もっと曲がりくねっていたようです。降雨のときなどは水量も増して勝手気ままに流れ、川辺の農地や道を崩してきたようです。地元の古老は、今でも暴れ川という人もいます。水の量も今より多かったようです。水量が少なくなったのは、上流の開発による森林の減少などが考えられます。 |
 |
あやせの由来について |
 |
あやせの地名は、明治の町村合併以前は文献には見られませんでした。明治の合併の時に始めて今の地名が用いられたようです。目久尻川を始め各河川の流れは、今の様な整備以前は川の瀬があやのように入り組んでいた事から「あやせ」の名が出たようです。なお、当市には目久尻川のほかに蓼川・比留川という2つの川があり、夫々地形の関係で入り組んだ流れをしていたものと推測されます。この様な川の現状から「あやせ」の名を冠したものと思われます。(明治22年町村制施行による) |
 |
古い人家と川(谷川)・山、森等の関係について |
 |
目久尻川の川辺には、古くからの人家が小高い丘と言ってもよい様な所と平地の境の所に多く見られます。これは、この地方だけのものだけではなく、私の出身地会津盆地に立って四方を見た時に、人家は必ず山と平地の境の所に部落として住居地域として発展した事が確認されています。また、その第一の条件は必ずそこに川が流れている事も重要な条件となっています。古代人は住居を定める時、水の存在を第一の条件にしたもの思われます。それは、生活用水は勿論のこと、谷川の水による山菜の採取、山に住む動物の捕獲による食材の確保が必要でした。また、集団で住む事は外からの危険から各自支えあいながら身を守ったと思われます。平地では身をかくす所を探すことが難しく、山の自然形態と樹木による自然の恵みを利用したようです。また、後世になって農耕が盛んになってからは、なお更のそのように思われます。川の魚を捕り、食糧とした事は当然のことと思われます。 |
|





